横須賀うみかぜ通信
cool head but warm heart
血液検査の正常範囲の決め方
尿酸を例にとりますと尿酸の正常範囲は男性で3〜7mg/dlなのですが、 どうしてこの範囲を正常と言うのか不思議に思いませんか? 正常範囲の決め方を簡単に説明しましょう。 例えば10000人の健康な男性の尿酸値を測定します。 これを縦線を人数、横線を尿酸値としてグラフを書きま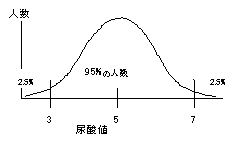 すと、なだらかな山型の分布(正確には正規分布)を示します。その頂上のところの尿酸値が健康男性で最も多い尿酸値で大体5mg/dlになります。 その頂上をはさんで両側に山の裾野が拡がっており、その裾野の高さ(つまり人数)に一致する尿酸値があるわけです。 ここで各裾野の一番端から数えて2.5%(10000人なら25人づつ)の部分の尿酸値を正常下限と正常上限と決めるのです。 こういう決め方をしているので、どんな健康な集団で尿酸値を測定しても2.5%の人は正常より下で2.5%の人は正常より上の値をとる、つまり健康な人の5%の人は“あなたの尿酸値は異常ですよ” と言われるのです。 臨床医学では経験的に確率が1/20(つまり5%)しか起こらない出来事を異常な出来事と決めており、血液検査の正常値の決め方もこの経験則に従っています。 血液検査が絶対的な指標ではないという意味がお分かりいただけましたか。 血液検査は相対的な指標で、 10%を基準にすれば、正常範囲は狭くなり、1%を基準にすれば正常範囲は広くなります。
すと、なだらかな山型の分布(正確には正規分布)を示します。その頂上のところの尿酸値が健康男性で最も多い尿酸値で大体5mg/dlになります。 その頂上をはさんで両側に山の裾野が拡がっており、その裾野の高さ(つまり人数)に一致する尿酸値があるわけです。 ここで各裾野の一番端から数えて2.5%(10000人なら25人づつ)の部分の尿酸値を正常下限と正常上限と決めるのです。 こういう決め方をしているので、どんな健康な集団で尿酸値を測定しても2.5%の人は正常より下で2.5%の人は正常より上の値をとる、つまり健康な人の5%の人は“あなたの尿酸値は異常ですよ” と言われるのです。 臨床医学では経験的に確率が1/20(つまり5%)しか起こらない出来事を異常な出来事と決めており、血液検査の正常値の決め方もこの経験則に従っています。 血液検査が絶対的な指標ではないという意味がお分かりいただけましたか。 血液検査は相対的な指標で、 10%を基準にすれば、正常範囲は狭くなり、1%を基準にすれば正常範囲は広くなります。
← 元に戻るには検査の簡単な説明をクリック